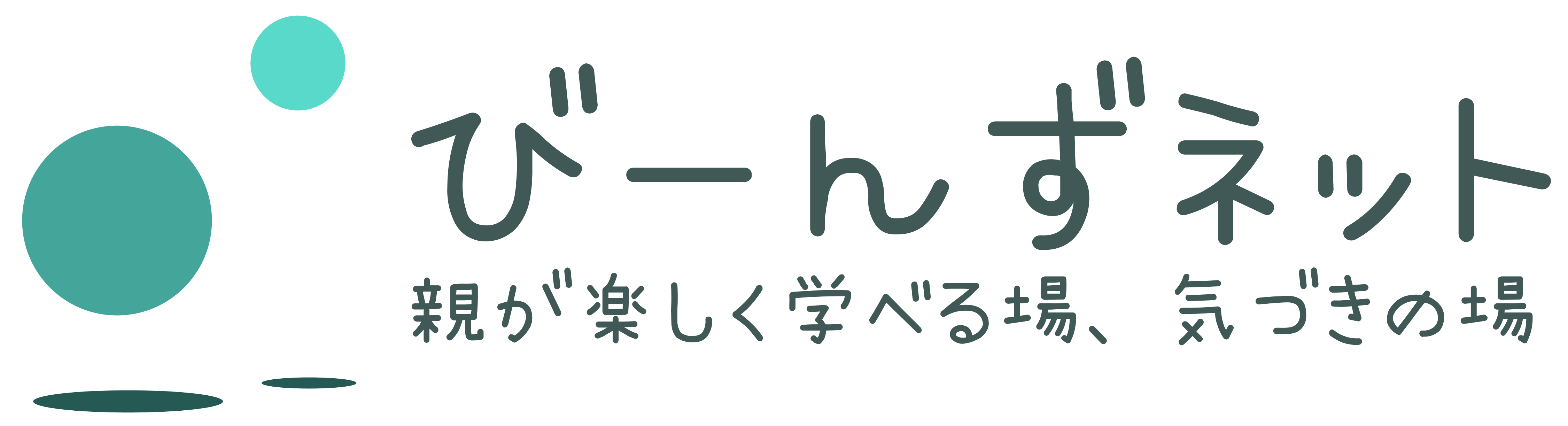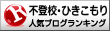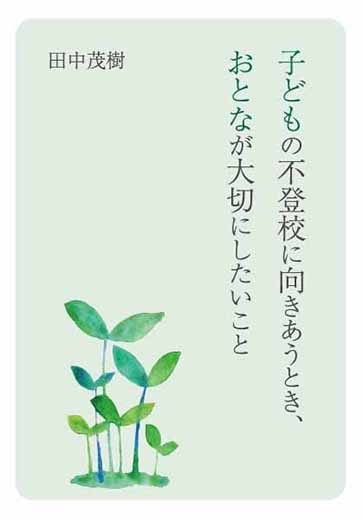「子どもが主体」の学びを広げる種まきを

びーんずメイトVol.33
夢みるプロジェクト@Mt.Fuji
一條いづみさん
静岡県富士市を中心に、学校と家庭、
そして地域をつなぐ活動をしている
「夢みるプロジェクト@Mt.Fuji」。
保護者、学校関係者、行政、
地域の方々と連携して、
子どもたちが「自分らしく学べる場」
を自由に選択できる社会の実現を
目指して活動しています。
代表の一條いづみさんにうかがいました。

夢プロ*サマースクールin大淵笹場2023前日準備の様子
――夢みるプロジェクト@Mt.Fujiを立ち上げたきっかけを教えてください。
2022年に富士市で初めて映画『夢みる小学校』の上映会を開催したんです。地元の先生たちにも登壇してもらったんですが、その会に集まった人たちと「子ども主体の学びを広げていこう」という思いが重なって。それで保護者と教員と、親の会の代表や地域の人たちと一緒に立ち上げたんです。
今、「夢プロ」のコアメンバーは10人くらいいます。先日の不登校サミットもこの夏に開催するサマースクールもそうですけど、イベントごとに「サポートしてくださる方、お願いします」って募集をかけるんです。そうすると20人、30人と集まってくれる――「循環型スタイルの市民団体」と謳ってますけど、企画ごとに同じ思いの仲間とつながって、一緒につくっていくのがこの団体の特徴です。
みんな思いがあってやっている人たちなので、それだけエネルギーも熱量も高いんですね。

夢みるプロジェクト@Mt.Fuji代表 一條いづみさん
一緒に子どもたちのことを考えたい
去年は立ち上げ一年目でいろんなことをやってきたんですけど、「これは継続したい」という企画を今年もピックアップしておこなっています。夏休みと冬休みの学校の先生たちとの「対話会」も恒例で。
――それはどういう思いからですか?
やっぱり子どもを真ん中に置いたときに、チームとして一緒に考えていきたいという思いが根底にあります。何か問題が起きたときに、学校と家庭が敵同士であってはいけないじゃないですか?
コロナ以降もそうですけど、学校だと保護者が先生とお話しする機会って、面談の15分くらいなんですよね。そこでどれだけのことを伝えられるかって言ったら、たぶん難しいと思うんです。
だけど対話会でざっくばらんに話せば「あ、なんだ。先生そんなことを思ってたんだ」とか、「保護者はこんなことが知りたいんだ」と気づくことができる。
たとえば先生に電話するタイミングってお母さんたちも迷うじゃないですか? でも対話会に来ている先生に聞けば「何時ぐらいがいいと思うよ」って教えてくれるから、そのタイミングでかけてみようとか。そうやって相手の環境を理解していくというか、もっとお互いにコミュニケーションをとって一緒に子どもたちのことを考えていけるといいなって。

2024年5月19日に開催した「ふじ不登校サミット2024」。多数の保護者や教育関係者ら200名以上が来場した。
この前、「中学校に制服を着ていきたくない」という息子さんのことで悩んでいるお母さんがいらしたんですよね。なので「制服を着ていかない中2の子、うちにいますけど」ってお伝えしたんですよ。
私の娘には聴覚過敏や感覚過敏があって、小学2年のころから学校に行き渋ることがあったんです。学校で頑張ってすごく疲れていたんですよね。お布団の中で毎日泣いていたり……。私もすごく葛藤して何度も涙を流したこともあったんですけど、当時の校長先生をはじめ、先生方がとても理解してくださったんです。娘は養護教諭の先生が大好きで、5年生まで“保健室登校の皆勤賞”だったんですよ。
中学にあがる前の春休みに、「こういう事情で制服を着るのは苦しいので、着なくてもいいですか?」って中学校に相談したんです。小学校の担任の先生経由で事前に伝えてもらっていたのもあったので、すんなり二つ返事でOKで。なのでうちは学用品も一切買ってないんですよ。それも言ってだめなら仕方ないけど……。
――確かに、言ってみないとお互いにわからないですよね。
そうなんです。まず「そういう声もあるんだな」と学校が認識するチャンスでもあるので、「まず言ってみようよ」ってお母さんたちにはよく話しますね。
それから不登校サミットを機につくった「地域つながりマップ」のようなツールですよね。子どもたちの居場所や学び場を可視化したものですけど、これを地域のコミュニティカフェになっているタリーズコーヒー(富士市中央公園店)に置いてもらって、必要なときに誰でもさっと手に取れるようにしたんです。誰がいつなんどき、どんな状況で悩むかわからないので。

一條さんの娘Asatoさんも取材に同席。サマースクールのチラシデザインを担当するなど、夢プロkidsのメンバーとして活躍中。
自分らしく元気に幸せでいられたら
――イベントもそのきっかけづくりのひとつなんですね。
「不登校サミット」を主催して、中には「不登校支援団体なの?」と言われることもありますけど、実はそれだけではなくて。
多様な子どもたちがいる中に学校に行かないという選択をした子たちがいる。その背景にHSCの子がいたり、起立性調節障害の子がいたり――不登校に限らずいろんな子どもたちが、自分らしく元気に幸せでいられたらいいよねって。
そのために地域で子どもたちのいろんな学びの選択肢を増やしていこうと。日々の活動をつなげて、お母さんたちの考え方をちょっとでもアップデートできたらいいなと思っています。その種まきをこれからも同じ思いを持つメンバーとともに続けていきたいですね。

先生たちとの「対話会」で。それぞれの課題を持ち寄りみんなで考える。学校と家庭、地域がつながる場にもなっている。
夢みるプロジェクト@Mt.Fuji
夢プロ事務局 yumepro.fuji@gmail.com
SNSで様々な情報を発信中
LINEオープンチャット
Facobook
Instagram
金子(A)

ブログランキングに登録しています。
応援いただけたら嬉しいです。クリックお願いします。
子どもの不登校に向き合うとき、おとなが大切にしたいこと
その著者・田中茂樹さんをゲストにお迎えした2022年8月のびーんずネットのセミナー内容を書籍化しました。
「待つしかないのでしょうか?」
「昼夜逆転、ゲームだらけの毎日に不安」
「甘やかしと見守りの違いがわからない」
など、不登校の子を持つ同じような悩みを持つ方にとって、田中先生の回答は非常に参考になるはずです。